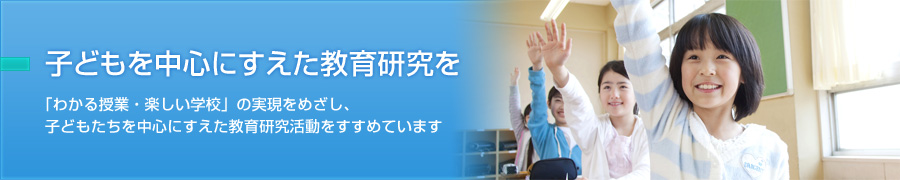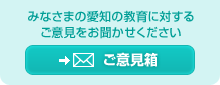第64次愛知県教育研究集会
2015/01/20
- 分科会(各科目についての報告は下の表からご覧下さい。)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基調報告より
現在、各学校では子どもたちの健やかな成長を願い、日々教育活動に取り組んでいます。
これまでの63次にわたる教育研究活動において、わたくしたちは夢と希望あふれる教育の創造をめざし、子どもたちを中心にすえ、それぞれの学校・地域の特色を生かした、自主的・主体的な教育研究活動を着実に積み重ねてきました。また、保護者への意識調査を実施し、今日的な教育課題を明らかにするとともに、各地域で教育対話集会などを行い、保護者や地域の方々と意見交換をする中で、子どもたちの「生きる力」を育む取り組みについての合意形成をはかってきました。
わたくしたちは「学力」とは単なる知識の量としてはかるものではなく、体験や知識をもとに、自ら課題を見つけ、判断し、行動することのできる力、学ぶ意欲も含めた総合的な力でなければならないと考えています。そのためにも「生きる力」をゆとりとふれあいの中でじっくりと育んでいかなければなりません。
わたくしたちは、すべての子どもたちに「生きる力」を育むために、学校・家庭・地域の連携をよりいっそう強化し、地域ぐるみの教育を推しすすめていかなければなりません。そのためにも、基礎・基本の確実な定着はもちろんのこと、知識がつめこまれるような学びではなく、子どもたち一人ひとりが学ぶ意欲をもち、自らすすんで取り組む質の高い学びを大切にするとともに、人・自然・文化などとかかわり合い、地域に根ざした体験活動を中心にした学習を構築していく必要があります。
今次の教育研究活動においても、ゆとりとふれあいの中で「わかる授業・楽しい学校」の実現をめざし、「学びの質を追究するとともに、子どもたち一人ひとりの意欲を大切にし、学ぶ喜び・わかる楽しさを保障する教育課程編成活動をすすめる」「学校・地域の特色を生かし、人・自然・文化などとのかかわりを大切にした創意あふれる教育課程編成活動をすすめる」の2点を研究推進の重点として提起しました。わたくしたちがすすめる教育改革は、日々の教育実践を積み重ね、その中で成長していく子どもたちの姿で示すべきだと考えます。各分科会においては、実践研究の報告をもとにして、活発な議論を展開するとともに、その成果を各単組・各分会にもち帰り、還流をはかっていただくことを大いに期待します。
また、本日の特別集会では、子どもたちの現状や最近の教育をめぐる情勢をふまえ、「大切な存在であることを伝えよう~子どもたちの『自尊感情』を高めるために~」と題して、記念講演を行います。子どもたち自信が大切にされていると実感することの必要性や子どもたちの学びや育ちを支えるために、学校・家庭・地域がいかに連携していくかについて、参加者のみなさまとともに考え、共通理解をはかる場にしたいと考えます。
最後になりましたが、この教育研究愛知県集会が愛知の教育のさらなる推進のため、そして、何よりも目の前の子どもたちの健やかな成長のために、実り多いものとなることを祈念し、本集会開会にあたっての基調報告といたします。
分科会
国語教育(文学その他)
説明的文章4本と、文学的文章30本のリポートが報告された。目の前の子どもたちの実態を見つめた地道な実践が多く、どのように読む力をつけるべきかについて、報告されたリポートをもとに討論が展開された。
国語教育(作文その他)
作文(綴り方)の教育14本と、言語の教育4本、音声表現の教育19本のリポートが報告された。目の前の子どもたちの実態を見つめて、どのような子どもを育てるのか、文字言語・音声言語のよさを生かして、どのような力を育てていくのかについて討論が展開された。
外国語教育
今次は、「小学校外国語活動」「表現する力を育てる活動」「わかる・楽しい授業」の3つの柱ごとに全員発表の形式で行われた。
小学校外国語活動では、外国語に慣れ親しみながら、自分の思いや考えを表現するといった発展的な実践が多く報告された。外国語を学習することを通して、意思形成力を育む支援のあり方や、よりよい学習集団づくり、子どもたちの意欲を引き出し達成感を得られる活動などについて、議論が展開された。
社会科教育(小学校)
身近な地域の産業や事象を教材化したり、学習活動を工夫して子どもたちの追究意欲を高めようとしたりした実践が報告された。 また、社会に主体的にかかわっていこうとする、主権者意識を高めることに取り組んだ実践が報告された。
討論では、社会に参画する力とはどのような力であり、そのために必要な社会認識をどう育てるかについて、熱心に話し合われた。
社会科教育(中学校)
子どもたちが主体的に取り組む学習活動のあり方についての実践、社会に対する見方・考え方を深める学習活動のあり方についての実践が報告された。
学ぶ意欲を高めるための学習活動を工夫した実践、学ぶ意欲を持続させ、子どもが主体的に課題を追究していく実践、地域素材をはじめとする身近な素材を教材化し、子どもの社会認識を深め、社会に参画していこうとする意識を育む実践が多く報告された。
数学教育(算数)
「思考力・判断力・表現力の育成」「わかる・できる指導の工夫」「学び合う力の育成」の3つの柱立てで、実践の報告や討論が行われた。どの報告も目の前の子どもを中心にすえ、子どもの力をのばしたいと感じることができるものであった。
討論では、ねらいに迫るために有効な教材の工夫や表現力を高めるためにはどのような手だてが有効なのかについて議論され、活発な意見交換がされた。
数学教育(数学)
「確かな学力の定着」「思考力・判断力・表現力の育成」「学習形態の工夫」「自ら学ぶ力・意欲の育成」の4つの柱立てで、実践の報告や討論が行われた。自ら学び、主体的に取り組む子どもの育成を主眼とした実践をはじめ、教材・教具の工夫、子どもの追究意欲が高まるようなICT機器を利用した実践、魅力ある課題やその掲示の工夫及び数学的活動を通して子どもの自発的な活動を引き出した実践など、多岐にわたる実践が報告された。
理科教育(物理・化学)
研究主題「子どもの発達段階をふまえた教育課程編成のあり方」「自然概念形成に有効な教材・教具の開発、指導の工夫」「単元における『ものづくり』の扱い方」「基礎・基本の習得と評価のあり方」「理科教育の意義」の5つを柱立てに、29本のリポート報告にもとづきながら、テーマ別討議や全体討論が活発に行われた。
理科教育(生物・地学)
身近な自然に目を向けさせ教材化する実践、飼育・栽培活動を継続的に行う実践、モデルを取り入れることによって子どもたちに空間概念を養わせる実践、条件や視点を明確にし、共有することで考えを深める実践などが報告された。
討論では「基礎・基本を重視した教育課程編成のあり方」「地域の素材の教材化」「子どもの視点に立った教材・教具の開発」「子どもたちに理科の有用性を実感させる指導のあり方」について活発な意見が出された。その中で、科学的な事象を理解するためには、科学的な用語の意味を正確に理解することと、それらを使って文を構成する力を養うことが重要であると確認された。
また、近年では地学分野での実践が少なくなっており、今後は地学分野の実践にもっと取り組む必要があるということも確認された。
生活科教育
探検活動を通して地域の自然や人々とのかかわりを深める実践、異学年交流や幼・保・小の連携を通して、豊かな学校生活を送ることができるようにする実践、飼育・栽培活動を通して動植物への愛着を深める実践などが報告された。
子どもたちがいきいきと活動する様子がよくわかる実践が多かった。また、子どもが活動したことをもとにして、内容や自分の考えなどを伝え合うことを通して、子どもたちの気付きの質が高まっていく様子も多く報告された。生活科を通して、子どもたちの自立の基礎が養われていく確かな実践がすすめられていることが感じられた。
美術教育
「美術教育を通して子どもたちに伝えたいこと」をテーマに実践報告や討論がすすめられた。
総括討論では、日々、教員が感じていることや、子どもたちの実態をふまえ、図工・美術教育から何を学ばせるのかという論議を通して、本年度のテーマを深めることができた。
制作活動中に子どもが感じる不安や悩み、「うまくつくりたい、表現したい」という子どもの思いを受け止め、教員がどのように支援するべきなのかという点について話し合われた。また、子どもたちの将来を見据え、義務教育の中で小・中がどのように連携し、子どもの表現力を高めていくのか、美術教育では、将来にむけてどんな力を育んでいくのかという論議などを通して、わたくしたち美術教員が常日頃考えなければならない課題を再確認することができた。
音楽教育
「音楽表現を高めるためのコミュニケーションのあり方」「子どもの思いや意図を表現に生かすための指導の工夫」をテーマに討論をすすめた。音楽の学習を通して互いのよさを認め合う実践が多く報告され、音楽教育によって培われる「生きる力」について深く考えることができた。
午前中は、DVDによる実践報告を行った。どの報告もめざす子ども像を明確にし、実践を通して変容していく様子をよくとらえたものであった。
小学校低学年では、子どもどうしのかかわり合いを大切にし、リズムを学校生活のさまざまな場面で取り入れた実践、拍の流れを感じ取り、音楽表現を楽しむ実践が多く報告された。
小学校中・高学年では、聴く活動を通して、互いの音楽表現のよさを認め合う実践、音楽を形づくっている要素に着目し、表現や鑑賞に生かす実践が多く報告された。
中学校では、音楽を形づくっている要素が楽曲に与える効果について考える鑑賞の実践などが報告された。
技術教育
知識や技能を習得し、生活に生かす実践が多く報告された。材料と加工では、加工精度が求められる組みつぎを使った製作活動に取り組んだ実践、知識や技能を共有することで、主体的に課題追究に取り組んだ実践、正しく製作図をかき、見通しをもって製作活動に取り組んだ実践が報告された。エネルギー変換では、視覚的にとらえ、学習内容を理解させることで、主体的に学習に取り組んだ実践、協力して課題追究した実践、家庭科分野と連携しながら、機構について取り組んだ実践、比較実験や回路実験を通して、基礎的・基本的な知識や技能を身につけた実践が報告された。生物育成では、牛乳パックで鉢をつくり、リーフレタスの栽培を行った実践、ティーム・ティーチングの形態をとりながら、簡易水田での稲作を行った実践、ミニチュアハウスを製作し、冬場にミニトマトの栽培を行った実践が報告された。情報と技術では、疑似体験をし、情報モラルについての理解を深めた実践、プログラムの作成やデジタル作品の製作を行った実践、疑似体験を通して、問題解決的な授業を展開した実践が報告された。技術教育全般では、LEDの光を用いたリーフレタス栽培に取り組んだ実践、ICT機器を整備し、学習場面に応じて活用した実践が報告された。
家庭科教育
子どもの実態をとらえ、生活の中から課題を見つけることから学びをはじめた実践が多くみられた。実験や実習などを多く取り入れ、五感を働かせる実体験を重視した実践、対話や討論を積極的に取り入れて、互いの考えを交流させる場を工夫した実践も多くみられた。また、持続可能な社会の一員として、よりよい生活を送ろうとしたり、防災意識を高めたりするなど、現代的な課題に取り組んだ実践も報告された。これらの実践をもとに、具体的な討論を行うことができた。
保健体育(体育)
「体育でどのような子どもを育てるか、自ら考え行動する子どもをどう育てるか」を大テーマに、次の点を研究主題として、発表・討論が行われた。
⑴ かかわり合いを大切にした授業づくり
⑵ 学年に応じた体力向上と技能習得
どのリポートにも、仲間とのかかわり方や学年に応じた体力向上と技能習得に関して、さまざまな工夫のある実践が報告された。
討論では、かかわり方を系統的に見て、それぞれの学年で習得していくべき内容について活発な意見交換がなされた。また、技能習得のためのよりよい指導法などについて、活発な意見が出された。
保健体育(保健)
「子どもが生活の主体となるための健康教育」をテーマに、さまざまな健康課題に対応するために教材・教具を工夫した実践、子どもの主体的な取り組みを中心とした実践、話し合い活動を取り入れた実践などが報告された。報告を通して、健康に対する意識の高まりや健康課題の解決にむけての実践力が着実に育ってきている様子が感じられた。
自治的諸活動と生活指導(小学校)
「たくましく生きる子どもを育てよう」をテーマとして、活発に討論された。
子どもたちのよりよい人間関係を築くために、学級や学年、異学年交流などを通して活動する実践が多く報告された。また、子どもたちが自分自身を見つめ、自ら課題を見つけて取り組むことで、豊かな人間性を身につけていく実践も報告された。さらに、学校と家庭、地域社会が連携して一人ひとりの子どもを支援していく実践なども報告された。
これらの実践報告をもとに、子どもたちの活動のあり方や意義、子どもたちの実態のとらえ方、それらをふまえた教員の支援のあり方について熱心な討論が展開された。
自治的諸活動と生活指導(中学校)
「たくましく生きる子どもを育てよう」をテーマに、活発な討論がなされた。
人権について考える実践、生徒のやる気を引き出すために自己存在感を大切にした実践、学校行事を生かしながら、個と集団の力を高める活動や生徒会活動、家庭・地域と連携した活動を通じて、子どもの成長をめざす実践が報告された。
これらの実践報告をもとに子どもたちの実態をふまえた支援のあり方について議論が深められた。
能力・発達・学習と評価
子どもたちの対話力を育むために、聴き合い学び合う学級づくりに取り組んだ実践や、自分の考えをもち、かかわり合いながら学ぶことで、課題解決をめざした実践、ユニバーサルデザインの考えをもとに、個に応じた授業の工夫をした実践が報告された。地域と連携し、ふるさとのよさを体感することで、思いを形にし発信していく場を設定した実践、外部講師と連携し、命の大切さを実感する実践、ICT機器を効果的に活用することで、確かな学力を身につけることをねらった実践が報告された。
特別支援教育
「豊かに生きるための力を育む」というテーマのもとに35本のリポートが報告された。
子どもの教育的ニーズを的確に把握し、学習意欲を高めるような教材・教具を工夫した実践、子どもの現在や将来の生活に直接結びつく力を身につけさせるための実践、人とかかわる力やコミュニケーション能力を高めるための実践などが報告された。
進路指導
小学校では、通級指導を通してコミュニケーション能力を育成したり、自己肯定感を高めさせたりする実践が報告された。少人数指導でコミュニケーションスキルの定着をはかることによって、子どもは自信をもって仲間とかかわれるようになることが確認された。
中学校では、職場体験学習を軸として、事前・事後の指導を系統的に行う実践や、「生きる力」を培うために、進路にかかわる行事を系統的に行う実践が報告された。ディスカッションや調べ学習を通して、さまざまな職業について子どもたちに主体的に学ばせることで、職場体験学習がより有意義なものになることが確認された。
教育条件整備
「子どもの学習権の保障のために」を主題に、ICT教育にかかわる条件整備、防災教育にかかわる条件整備、個に応じた教育環境にかかわる条件整備についての実践が報告された。
ICT機器を効果的に活用して子どもの学習意欲を高めた実践、体験学習を通して地域との連携を高めた実践が報告された。また、地震に対する備えや対応マニュアルの問題点をアンケートによる調査からまとめた実践や、学校の施設・設備に関する実情をアンケートによる調査からまとめた実践も報告され、熱心な討論が行われた。
過密・過疎、へき地の教育
コミュニケーション能力を高める実践、複式学級の授業にガイド学習を取り入れた実践、地域素材や人材を積極的に活用した実践など4本が報告された。
どの学校も児童数が減少しており、人とのかかわりが内向的になるという傾向がみられた。そこで、「話す」「聞く」「伝え合う」場面を多く設定し、自分の考えを発表する機会を増やして自信をもたせる実践が報告された。また、地域素材を生かした体験的な学習を通して、地域の特色やよさを見つめ直させる実践が報告された。
いずれの実践も、へき地校の抱える問題点を考慮しながら、小規模校の利点を生かし、地域素材や人材を活用した実践であった。
環境問題と教育
学校や地域の特色をふまえ身近な環境問題を取り上げた実践、「小さな地球モデル」や「トイレカード」など環境問題に関する教材・教具や、地域・企業・行政などの人材を積極的に活用した実践が、小学校から3本、中学校から4本報告された。
子どもたちの環境問題に対する意識を高め、環境問題を他人事としてではなく自分事としてとらえさせ、よりよい環境づくり、持続可能な社会をめざして、家庭や地域を巻き込みながら積極的に実践に取り組んでいる様子がうかがえた。
情報化社会の教育
課題提示や発表方法を工夫することで、必要な情報を収集・整理したり、相手を意識した情報発信をしたりするといった情報活用能力を育成する実践が報告された。
また、各教科の授業でICT機器やデジタルコンテンツを有効に活用することで、学習意欲や学習理解の向上をはかりながら学習のねらいに迫る実践が報告された。
さらに、子どもの実態を把握し、実際に起きているインターネット上の問題を教材化することで、情報モラルについての意識や態度を育てる実践が報告された。
助言者からは、各実践にかかわらせながら、情報活用能力の育成やICT機器活用のポイント、情報モラル育成のために配慮すべきことについて具体的な助言を得た。子どもを中心にすえた実践から学び、考えることができ実り多い分科会となった。
読書・学校図書館
学校間、地域間で差はあるものの、図書館の環境整備がすすむなか、公共図書館や学校司書との連携をはかりながら、読書に親しませる実践が行われている。しかし、図書館を各教科などで利用するための年間活用計画や、図書資料を提供するための環境整備はまだ十分でないことが討論を通して確認された。
子どもたちの「生きる力」を養うために工夫された読書活動や、各教科と関連づけた授業、学習情報センターとしての図書館の利用などの実践が数多く報告された。
総合学習
体験活動を通して、生き方を見つめ直し、将来を切り開いていこうとする子どもたちの育成をめざした実践が多く報告された。子どもの意見や考えを整理・分析するための手だてとして、イメージマップやXチャートなど、さまざまな思考ツールが紹介された。「総合的な学習の時間」が縮減されたものの、各教科・他学年との関連や小・中連携をはかる実践から、総合学習の役割を再確認する必要があることが確認された。
カテゴリー:更新情報, 教育研究愛知県集会 →2022年以降の記事は愛教組連合ホームページへ, 子どもを中心にすえた教育研究を