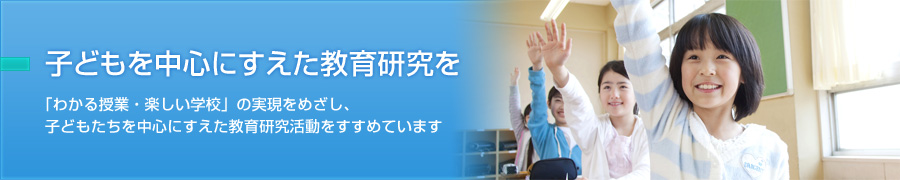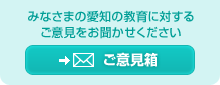第67次愛知県教育研究集会
2017/10/21
10月21日、約1600人の教員や保護者、働く仲間の参加のもと、第67次教育研究愛知県集会が開催されました。
全体集会の後には、「子どもたちの健やかな成長をめざして」をテーマに特別集会が行われました。特別集会では、プール学院大学教授の長尾彰夫先生から「学校・家庭・地域の協働」という題目で記念講演をいただき、参加者との意見交換が行われました。
また、27の分科会では、子どもたちを中心にすえた実践報告と活発な討論が行われました。
- 分科会(各科目についての報告は下の表からご覧下さい。)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基調報告より
これまでの66次にわたる教育研究において、わたくしたちは夢と希望あふれる教育の創造をめざし、子どもたちを中心にすえ、それぞれの学校・地域の特色を生かした、自主的・主体的な教育研究活動を着実に積み重ねてきました。また、保護者への意識調査を実施し、今日的な教育課題を明らかにするとともに、各地域で教育対話集会などを行い、保護者や地域の方々と意見交換をする中で、子どもたちの「生きる力」を育む取り組みについての合意形成をはかってきました。そして、各学校では子どもたちの健やかな成長を願い、日々教育活動に取り組んでいます。
さて、現在、国が推しすすめるさまざまな教育改革の波は学校現場にも大きな影響を与えようとしています。とりわけ、文部科学省が3月に公示した新学習指導要領では、小学校高学年において英語を教科化し、中学年に外国語活動を導入するとしています。学習内容も過去形や動名詞が加わるなど、中学校英語の前倒しや知識の習得そのものが目的となることが危惧されます。また、現在の小学校における週あたりの総授業時数はすでに限界がきており、年間授業時数が35時間増えることは、子どもたちの負担がいたずらに増えるのみとなり、ゆとりとふれあいの中で「生きる力」を育む教育の軽視につながりかねないと考えます。子どもたちに必要な力は、英語力を身につけることだけではなく、自ら課題を見つけ、主体的に判断し、行動できる「生きる力」であり、ゆとりとふれあいを保障する教育課程の中で育てていかなければなりません。
このようなときだからこそ、わたくしたちは、あくまでも学習指導要領を大綱的基準としてとらえ、未来を担うすべての子どもたちのために夢と希望あふれる教育を創造する取り組みを継続し、学校現場からの教育改革を推進していかなければなりません。そのためにも、基礎・基本の確実な定着はもちろんのこと、子どもたち一人ひとりが学ぶ意欲をもち、自らすすんで取り組むより質の高い学びを大切にしていかなければなりません。また、人・自然・文化などとかかわり合い、地域に根ざした体験活動を中心にした学習を構築し、学校・家庭・地域の連携をよりいっそう強化し、地域ぐるみの教育を推しすすめていかなければなりません。
今次の教育研究活動においても、ゆとりとふれあいの中で「わかる授業・楽しい学校」の実現をめざし、「学びの質をより追究するとともに、子どもたち一人ひとりの意欲を大切にし、学ぶ喜び・わかる楽しさを保障する教育課程編成活動をすすめる」「学校・地域の特色を生かし、人・自然・文化などとのかかわりを大切にした創意あふれる教育課程編成活動をすすめる」の2点を研究推進の重点として提起しました。わたくしたちがすすめる教育改革は、日々の教育実践を積み重ね、その中で成長していく子どもたちの姿で示すべきだと考えます。各分科会においては、実践研究の報告をもとにして、活発な議論を展開するとともに、その成果を各教組・各分会にもち帰り、還流をはかっていただくことを大いに期待します。
また、本日の特別集会では、子どもたちの現状や最近の教育をめぐる情勢をふまえ、「学校・家庭・地域の協働-未来を担う子どもたちのために-」と題して、記念講演を行います。未来を担う子どもたちの健やかな成長をめざして学校・家庭・地域で大切にしていきたいことなどについて共通理解をはかり、それぞれがいかに協働して子どもたちを育てていくか、ともに考えていきたいと思います。
最後になりましたが、この教育研究愛知県集会が愛知の教育のさらなる推進のため、そして何よりも目の前の子どもたちの健やかな成長のために、実り多いものとなることを祈念し、本集会開会にあたっての基調報告といたします。
分科会
国語教育(文学その他)
説明的文章9本と、文学的文章26本のリポートが報告された。目の前の子どもたちの実態を見つめた価値ある実践が多く、どのように読む力をつけるべきかについて、報告されたリポートをもとに討論が展開された。
国語教育(作文その他)
作文(綴り方)の教育8本と、言語の教育2本、音声表現の教育8本のリポートが報告された。子どもたちの実態を見つめ、どのような子どもを育てるのか、文字言語・音声言語のよさを生かして、どのような力を育てていくのか討論が展開された。
外国語教育
「小学校外国語活動」「4技能を育成する活動」「わかる・楽しい授業づくりのための工夫」の3つを柱に、小グループによる発表と討論が行われた。その後、各グループで設定された「全体討論への問題提起」をもとに、全体で討論と意見共有が行われた。
3つの小グループでは、小学校と合同授業を行った中学校の実践や、Can-Doリストを設定し、具体的な到達目標を明らかにして子どもたちの力を育てる実践などが報告された。子どもたちがお互いにかかわり合いながら、主体的に学習活動に取り組むための手だてが数多く報告され、活発な討論が行われた。
社会科教育(小学校)
地域素材を教材化したり、対話的活動を取り入れたりすることによって、主体的に社会に参画しようとする意欲を高める実践が報告された。
討論では、根拠をもとにした話し合い活動を通して育てたい力や、小学校段階で社会に参画する力を育てる意義などについて話し合われた。
社会科教育(中学校)
子どもたちが主権者として主体的に取り組む学習活動のあり方についての実践や、社会に対する見方・考え方を深める学習活動のあり方についての実践が報告された。
学ぶ意欲を持続させ子どもが主体的に課題を追究した実践や、地域素材をはじめとする身近な素材を教材化し、子どもの社会認識を深め、社会に参画していこうとする意識を育んだ実践が多く報告された。
数学教育(算数)
「思考力・判断力・表現力の育成」「わかる・できる指導の工夫」「学びあう力・意欲の育成」の3つの柱立てで、実践の報告や討論が行われた。
子どもたちが、主体的にかかわりあう姿をめざした実践や、ペア・グループ学習などの学習形態を工夫した実践、わかる喜び・できる楽しさを実感させるための手だてを工夫した実践、道筋を立てて考え、表現できるように工夫した実践などが報告された。どの報告も子どもを中心にすえ、子どもの力を伸ばしたいというねらいを感じることができるものであった。
数学教育(数学)
「思考力・判断力・表現力の育成」「確かな学力の定着」「自ら学ぶ力・意欲の育成、学びあう力の育成」の3つを柱に、実践の報告や討論が行われた。主体的に取り組む子どもの育成を主眼とした実践や、グループ学習やペア学習などの学習形態を工夫した実践、数学的活動を通して子どもの自主性を引き出した実践など、多岐にわたる実践が報告された。
理科教育(物理・化学)
「子どもの発達段階をふまえた教育課程編成のあり方」「自然概念形成に有効な教材・教具の開発、指導の工夫」の2観点に重点をおいた報告と討論を4つの設定分野・領域ごとに展開し、さらに「基礎・基本の習得と評価のあり方」「子どもたちに理科の有用性を実感させる指導のあり方」「単元における『ものづくり』の扱い方」を加えた5観点の柱立てによる総括討論を行うことで、より活発な意見交換がされた。
理科教育(生物・地学)
生命のつながりを実感できるような教材や飼育方法を工夫した実践、グループの形態を工夫し、対話的な学びを促した実践、モデルを取り入れることで実感を伴った理解をめざした実践などが報告された。
討論では、「子どもの発達段階をふまえた教育課程編成のあり方」「子どもの視点に立った教材・教具の開発や指導の工夫」の2観点を中心にして、「基礎・基本の習得と評価のあり方」「子どもたちに理科の有用性を実感させる指導のあり方」「地域の素材・人材の活用」を加えた5観点を柱立てに、活発な意見交換がされた。
生活科教育
スタートカリキュラムの実践や、幼・保・小で連携した実践、探検活動を通して地域の自然や人々とのかかわりを深める実践、継続的な飼育・栽培活動を通して、対象への愛着や自分自身への気付きを深める実践、季節ごとの自然を生かした遊びやおもちゃの製作を通して気付きの質を高める実践、家族の中での自分の役割を考え、よりよい生活を創り出そうとする実践などが報告された。
単元構想や手だてを工夫して、子どもたちがいきいきと活動し、思いや願いを実現する実践が多かった。また、友だちや地域の人々との交流を通して、思考を深めたり、気付きの質を高めたりする実践も多かった。
生活科を通して子どもたちの自立の基礎が養われていく確かな実践がすすめられていることが感じられた。
美術教育
「美術教育を通して子どもたちに伝えたいこと~子どもたちのゆたかな学びのために~」をテーマに実践報告や討論がすすめられた。
総括討論では、図工・美術教育から何を学ばせるのかという議論を通して、本年度のテーマについて考え、深めることができた。
図工や美術の授業(特に自画像制作)に対して子どもが抱える不安や悩み、思いを受け止め、教員がどのように支援していくとよいか話し合われた。また、子どもたちの将来を見据えて、小学校、中学校がどのように連携して、子どもの表現力を高めていくのか、美術教育では、将来にむけてどのような力を育んでいくのかという議論を通して、美術教員が考えなければならない課題を確認することができた。
音楽教育
「思いや意図を表現に生かし、高め合うための学習活動や指導の工夫」「習得・活用・探究の見通しをもち、学習のより深い理解や動機付けにつながる学習活動のあり方」をテーマに討論をすすめた。仲間と主体的・対話的にかかわり合いながら表現の工夫をする実践が多く報告され、発達段階に応じて音楽教育を行うことの大切さについて深く考えることができた。
午前中は、DVDによる実践報告を行った。どの報告も、めざす子ども像を明確にし、工夫を凝らした手だてによって、変容していく子どもたちの様子がよくわかるものであった。
技術教育
よりよい生活にむけて、学んだ知識や技能の活用をめざす実践が多く報告された。
エネルギー変換では、他教科と関連付け、学んだ知識を活用し、試行錯誤しながら電気回路を組み立てることをめざした実践や、マイ発電所づくりを行う中で、身につけた知識と技のよさを実感し、学びを生活の中で生かすことができる子どもの育成をめざした実践が報告された。
生物育成では、題材構想や学習過程、教材・教具を工夫し、子どもが意欲的に栽培技術を習得し、栽培の楽しさを実感させることをめざした実践が報告された。
情報では、センサカーを用いて、日常生活の中で最適解を求めることができる子どもの育成をめざした実践や、写真を使ったアニメーションづくりを通して、自ら課題を見つけ解決する子どもの育成をめざした実践が報告された。
技術教育全般では、主体的・対話的で深い学びの場面を確保するために、協働的な学習を取り入れた実践が報告された。また、伝統技能である「寄木加工」を取り入れ、子どもが達成感・満足感を得る中で「つくりたい」と思う気持ちを高めることをめざした実践が報告された。
家庭科教育
「知識・技能の習得」「生活を追究する」「家庭や地域、人とのつながり」の3つ柱立てで、実践の報告や討論が行われた。子どもの生活の中から課題を見つけ、学びを深めていく実践が多く報告された。
総括討論では、「主体的な家庭科の学び~よりよい生活や最適解を求め続ける取り組み~」について討論が行われた。
保健体育(体育)
「体育でどのような子どもを育てるか、自ら考え行動する子どもをどう育てるか」を大テーマに、次の2点を研究主題として、発表・討論が行われた。
(1)かかわり合いを大切にした授業づくり
(2)学年に応じた体力向上と技術習得
どのリポートも、仲間とのかかわり方や学年に応じた体力向上と技能習得に関して、さまざまな工夫のある実践が報告された。
討論では、かかわり方の有効な手だてや、子どもの発達段階に応じてどのような技能を習得させるべきかについて活発な意見交換がされた。また、技能習得のためのよりよい指導法などについて、活発な意見が出された。
保健体育(保健)
「子どもが生活の主体となるための健康教育」をテーマに、さまざまな健康課題に対応するため、教材・教具を工夫した実践や、子どもの主体的な活動を中心とした実践、学校内外との連携を深めた実践などが報告された。
自治的諸活動と生活指導(小学校)
「たくましく生きる子どもを育てよう」をテーマとして、活発に討論された。
子どもたちのよりよい人間関係を築くために、学級や学年、異学年交流を通して活動した実践が多く報告された。また、子どもたちが自分自身を見つめ、自ら課題を見つけて取り組むことで、達成感や成就感を味わい、豊かな人間性を身につけた実践も報告された。さらに、学校・家庭・地域が連携して一人ひとりの子どもを支援した実践なども報告された。
これらの実践報告をもとに、子どもたちの活動のあり方や意義、子どもたちの実態のとらえ方、それらをふまえた教員の支援のあり方について熱心な討論が展開された。
自治的諸活動と生活指導(中学校)
「たくましく生きる子どもを育てよう」をテーマに、活発に討論された。
子どものやる気を引き出すために自己存在感を大切にした実践や、学校行事を生かしながら、個と集団の力を高める活動、家庭・地域と連携した活動を通して、子どもの成長をめざした実践が報告された。
これらの実践報告をもとに、子どもたちの実態をふまえた支援のあり方について議論が深められた。
能力・発達・学習と評価
子どもたちが意欲的に学習課題に取り組み、主体的な学習を実現するための手だてとして、子どもにとって魅力的な課題を設定した実践や、ICT機器や思考ツールを用いた実践、多様な考えを引き出す道徳の実践などが報告された。
また、他者とのかかわりの中で学びを深めていく手だてとして、小グループでの話し合いを取り入れた実践や「話す・聞く」の約束事やルーブリックを取り入れた実践、保護者や地域の方の協力を得て行われた実践などが報告された。
特別支援教育
「豊かに生きるための力を育む」というテーマのもと、18本のリポートが報告された。
子どもの教育的ニーズを的確に把握し、学習意欲を高めるような教材・教具を工夫した実践や、子どもの現在や将来の生活に直接結びつく力を身につけさせるための実践、人とかかわる力やコミュニケーション能力を高めさせるための実践などが報告された。
進路指導
基礎的・汎用的能力の育成を重点に、学校や地域の特長を生かした教育の実践が報告された。
各教科、道徳、特別活動の実践では、子どもの発達段階に応じて協働的な問題解決の場面を設定し、主体的に学習に取り組む活動を通して、コミュニケーション能力、問題解決能力を育成できることが報告された。また、地域の特長を生かした実践では、人と人とのつながりを大切にした取り組みを通して、自己の生き方を主体的に考えることにつながることが確認された。
進路選択にむけた啓発的な実践では、指導者が子どもの視点に立って主体的な進路選択を支援する取り組みが報告された。
教育条件整備
「子どもの学習権の保障のために」を主題に、日本語教育にかかわる条件整備や、不登校児童生徒に対する人的配置の拡充における条件整備、ICT教育にかかわる教育条件整備についての実践が報告された。
外国にルーツをもつ子どもが過半数存在する学級で、全員が学習するための指導の工夫や課題、不登校児童生徒を支えるために必要な教育条件整備が報告された。また、ICT教育を充実させるため、現状の機器の整備や利用状況の調査結果と今後の課題が報告された。
過密・過疎、へき地の教育
どの学校の報告も、地域のよさをいかに生かし、子どもたちにどう気付かせ、愛着をもたせるかという点が共通していた。地域素材を生かして、地域の「ひと、もの、こと」にかかわることで、ふるさとのよさを再発見し愛着をもつ教育活動の実践がされていた。
また、小規模校では人間関係が固定されるため、他者とのかかわりが少なく、自分の考えに自信をもち、自己を表現することが苦手な傾向がある。そこで、他者とのつながりを感じ、自信をもって自分の考えを表現する実践が報告された。
いずれも、子どもに身につけさせたい力を明確にした上で、へき地校の抱える問題点を考慮しながら、小規模校の利点や、地域素材を生かした実践であった。
環境問題と教育
食を通して排出される二酸化炭素に関心をもち、二酸化炭素を排出しない食材選びや、二酸化炭素の排出を少なくする調理方法を体験することで、食と地球温暖化がかかわっていることに気付き、二酸化炭素を出さない生活をするために、自分にできることを考え、行動できる子どもの育成をめざした実践が報告された。
また、身近な環境問題を自分の体験を通して考える活動を加えたF-PDCAサイクルを基盤に、有用感をもって、すすんで環境問題に働きかける子どもの育成をめざした実践が報告された。
情報化社会の教育
主体的に学ぶためにICT機器を活用した実践や、プログラミング教育を取り入れた学びの実践などが報告された。また、子どもたちが主体的に情報モラルについて考え、身につけていく実践、体験や交流を通して、情報活用能力を高め、自信をもって相手に思いを伝える実践などが報告された。
読書・学校図書館
子どもたちが幅広いジャンルの本に出会うことをめざした実践が報告された。また、さまざまな分類の図書資料があることを子どもたちが知り、調べ学習に活用できるようにするための環境整備や配架の工夫について活発に話し合われた。子どもたちを取り巻く読書環境を充実させるためには、司書教諭、学校司書をはじめ、担任や図書ボランティアなどさまざまな人たちの連携が大切であることも確認された。
総合学習
目の前の子どもの興味・関心や思考の流れとその変化をとらえ、創意工夫を生かした教育活動を行いながら、めざす子どもの姿に迫る実践が多く報告された。子どもたちが学習課題を「自分ごと」として主体的に探究する総合学習の授業をめざし、教材と子どもとの出会いの工夫、ゲストティーチャーの有効な活用の仕方などが紹介された。探究的な学習のよさを理解したり、実社会の中から問いを見出したりするためには、地域社会とのかかわりを実感したり、学習課題に対し子どもが「自分ごと」として切実感をもったりするなど、学ぶ動機付けを意図的に喚起することが重要であると確認された。
カテゴリー:更新情報, 教育研究愛知県集会 →2022年以降の記事は愛教組連合ホームページへ, 子どもを中心にすえた教育研究を