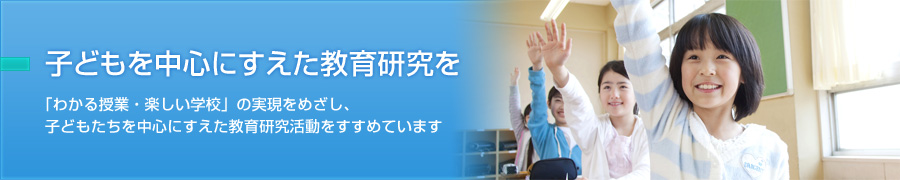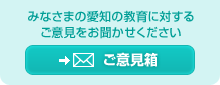第63次愛知県教育研究集会
2013/10/19
- 分科会(各科目についての報告は下の表からご覧下さい。)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基調報告より
現在、各学校では子どもたちの健やかな成長を願い、日々教育活動に取り組んでいます。
これまでの62次にわたる教育研究において、わたくしたちは夢と希望あふれる教育の創造をめざし、子どもたちを中心にすえ、それぞれの学校・地域の特色を生かした、自主的・主体的な研究を行ってきました。また、保護者への意識調査を実施し、今日的な教育課題を明らかにするとともに、各地域で教育対話集会などを行い、保護者や地域の方々と意見交換をする中で、子どもたちの「生きる力」を育む取り組みについての合意形成をはかってきました。
さて、政権交代による変革の波は、教育分野にも大きく及ぼうとしています。とりわけ、本年度、すべての中学校第3学年と小学校第6学年で行われた「全国学力・学習状況調査」については、結果の公表などにより、学校・地域の序列化につながっていくことが危惧されます。競い合いを容認しようとする動きは、知識偏重教育への回帰と言わざるを得ません。
学力は、単なる知識の量としてはかるものではなく、今までに得た知識や経験をもとに、自ら課題を見つけ、判断し、行動する力、学ぶ意欲も含めた総合的な力でなければなりません。そのためにも、「生きる力」をゆとりとふれあいの中でじっくりと育んでいかなければなりません。
わたくしたちは、すべての子どもたちに「生きる力」を育むために、学校・家庭・地域の連携をよりいっそう強化し、地域ぐるみの教育をすすめていく必要があります。学習指導要領をあくまでも大綱的基準としてとらえ、基礎・基本の確実な定着はもちろんのこと、学びの質の向上をめざす中で、子どもたち一人ひとりの意欲を大切にし、学ぶ喜び・わかる楽しさを保障することが重要と考えます。そして、子どもたちが地域の一員としての自覚をもち、人・自然・文化などとふれあいながら、自ら課題を見つけ、判断し、行動する力を身につけることができるよう、地域に根ざした学校現場からの教育改革を推進していく必要があります。
今次の教育研究活動においても、ゆとりとふれあいの中で「わかる授業・楽しい学校」の実現をめざし、「学びの質を追究し、子どもたち一人ひとりの意欲を大切にした、学ぶ喜び・わかる楽しさを保障する教育課程編成活動をすすめる」「学校・地域の特色を生かし、人・自然・文化などとのかかわりを大切にした創意あふれる教育課程編成活動をすすめる」の2点を研究推進の重点として提起しました。わたくしたちがすすめる教育改革は、日々の教育実践を積み重ね、その中で成長していく子どもたちの姿で示すべきだと考えます。各分科会においては、実践研究の報告をもとにして、活発な議論を展開するとともに、その成果を各単組・分会にもち帰り、還流をはかっていただくことを大いに期待します。
また、本日の特別集会では、子どもたちの現状や最近の教育をめぐる情勢をふまえ、-力と夢を育てる 地域ぐるみの学校づくり-と題して、記念講演を行います。学校・家庭・地域それぞれが主体性をもって、どのように子どもたちの学びや育ちを支えていくかについて、参加者のみなさまとともに考え、共通理解をはかる場にしたいと考えます。
最後になりましたが、この教育研究愛知県集会が愛知の教育のさらなる推進のため、そして何よりも目の前の子どもたちの健やかな成長のために、実り多いものとなることを祈念し、本集会開会にあたっての基調報告といたします。
分科会
分科会の様子





国語教育(文学その他)
説明的文章10本と、文学的文章34本のリポートが報告された。目の前の子どもたちの実態を見つめた地道な実践が多く、どのような教材で、どのように読む力をつけるべきかについて、報告されたリポートをもとに討論が展開された。
国語教育(作文その他)
作文(綴り方)の教育23本と、言語の教育2本、音声表現の教育20本のリポートが報告された。目の前の子どもたちの実態を見つめて、どのような子どもを育てるのか、文字言語・音声言語のよさを生かして、どのような力を育てていくのかについて討論が展開された。
外国語教育
今次は、「小学校外国語活動」「読む・書く活動」「コミュニケーション活動」「ICT機器の活用」の4つの柱ごとに全員発表の形式で行われた。
小学校第5・6学年における「外国語活動」の必修化の実施から3年目を迎えたこともあり、小学校での実践が多く発表され、小中の効果的な接続のための指導のあり方について活発な意見交換が行われた。
社会科教育(小学校)
身近な地域の産業や事象を教材化したり、学習活動を工夫して子どもたちの追究意欲を高めようとしたりした実践が報告された。 また、社会に主体的にかかわっていこうとする意識を高めることに取り組んだ実践が報告された。
討論では、ねらいに迫るために有効な学習活動の工夫や育てたい社会認識について、熱心に話し合われた。
社会科教育(中学校)
子どもたちが主体的に取り組む学習活動のあり方についての実践や、社会に対する見方・考え方を深める学習活動のあり方についての実践が報告された。
学ぶ意欲を高めるための学習活動を工夫した実践や、学ぶ意欲を持続させ、子どもが主体的に課題を追究していく実践、地域素材をはじめとする身近な素材を教材化し、子どもの社会認識を深め、社会に参画していこうとする意識を育む実践が多く報告された。
数学教育(算数)
「思考力・判断力・表現力の育成」「わかる・できる指導の工夫」「学び合う力の育成」の3つの柱立てで、実践の報告や討論が行われた。どの報告も目の前の子どもを中心にすえ、子どもの力を伸ばしたいと感じることのできるものであった。
討論では、自力解決に至るまでの指導の工夫や表現力を高めるためにはどのような手だてが有効なのかについて議論され、活発な意見交換が行われた。
数学教育(数学)
「確かな学力の定着」「数学的な見方・考え方の育成」「学習形態の工夫」「自ら学ぶ力・意欲の育成」の4つの柱立てで、実践の報告や討論が行われた。自ら学び、主体的に取り組む子どもの育成を主眼としたリポートをはじめ、教材・教具の工夫、子どもの追究意欲が高まるようなICTを利用した実践、魅力ある課題やその掲示の工夫及び数学的活動を通して子どもの自発的な活動を引き出した実践など、多岐にわたる実践が報告された。
理科教育(物理・化学)
研究主題の「子どもの発達段階をふまえた教育課程編成のあり方」「自然概念形成に有効な教材・教具の開発、指導の工夫」「単元における『ものづくり』の扱い方」「基礎・基本の習得と評価のあり方」「理科教育の意義」を柱立てに、40本のリポート報告にもとづきながら、テーマ別討議や全体討論が活発に行われた。
理科教育(生物・地学)
身近な自然に目を向けさせ教材化する実践、飼育・栽培活動を継続的に行う実践、マクロな自然現象のモデル化により子どもたちの理解を深める実践、条件や視点を明確にし、共有することで考えを深める実践などが報告された。
討論では「基礎・基本を重視するカリキュラムのあり方」「地域の素材・人材の教材化」「子どもの視点に立った教材・教具の開発」「子どもたちに理科の有用性を実感させる指導のあり方」などについて活発な意見が出された。その中で、科学的な事実を理解するためには、用語の意味を正確にとらえることと、それらを使って文を構成する力を養うことが重要であることが確認された。
また、近年では地学分野での実践が少なくなっており、今後は地学分野の実践にもっと取り組む必要があるということも確認された。
生活科教育
地域の自然や人々とのかかわりを深める実践、試行錯誤しながら、おもちゃづくりを通して工夫することの楽しさに気付く実践、自分の思いや願いをもって栽培活動に取り組む実践が多く報告された。
多くの実践は、伝え合いや話し合いを通して、主体的に動ける子どもを育てることや、子どもたちの気付きの質を高めることをねらいとしたものであった。
美術教育
「美術教育を通して子どもたちに伝えたいこと」をテーマに実践報告や討論がすすめられた。
総括討論では、授業の中で教員が感じていることや子どもたちの実態に迫る論議を通して、本年度のテーマを深めることができた。
「体験不足」「自信がもてない子ども」「発想を豊かにする難しさ」などの課題となる実態を認識し、「試行錯誤しながら、自分たちで問題を解決していく姿」や「他教材や地域社会とのかかわりから、興味や関心を深めていく姿」などの子どもたちの可能性に目を向けた話し合いが行われ、子どもたちに身につけさせたい力とは何かを考えることができた。
音楽教育
音楽の授業におけるコミュニケーションのあり方、子どもの意欲や子どもがもつ力をのばすためのよりよい教材選択や指導方法の工夫をテーマに討論をすすめた。また、音楽の学習における「楽しさ」についても考えを深めることができた。
小学校低学年では、リズムや拍の流れを身体表現や音楽遊びで感じ取る活動や、そのような活動で身につけたリズム感や拍感を歌唱表現に生かす実践が多く報告された。
小学校中学年では、歌唱表現の基礎・基本を身につけ、自分の思いや意図を表現する実践や、音楽のしくみを支えとした音楽づくりの実践が報告された。
小学校高学年では、要素に着目しながら鑑賞し、感じ取ったことを歌唱や器楽、音楽づくりに生かす実践が多く報告された。
中学校では、歌詞や作曲者の意図に着目してより深く楽曲を理解し、それを歌唱表現に生かした実践が多く報告された。
技術教育
知識や技能を習得し、生活に生かす実践が多く報告された。材料と加工では、試作を行い、自分の作品のイメージをもたせる実践、作業時間の差を少なくして、時間内に作業を完成することで達成感を味わわせる実践が報告された。エネルギー変換では、蒸気タービンカーを製作し、効率的な発電を追究する実践、学習課題を小集団で追究することで意欲的な話し合いができた実践が報告された。生物育成では、三十日大根を教室で栽培した実践、簡易水田をつくり、生育環境を追究した実践が報告された。情報と技術では、複数のメディアを適切に選択し、受け手にわかりやすく伝えることを意識した実践、スモールステップで学習をすることで、プログラムの理解を深めた実践が報告された。これらの実践をもとに、具体的な討論を行うことができた。
家庭科教育
子どもの興味・関心から対話や討論を積極的に取り入れた実践が数多くみられた。また、実験や実習、調査活動を取り入れ、その手順と理由をていねいに追究する実践も報告された。また、生活を主体的につくる資質や能力を育むための実践や、生活をしっかり受け止め、それを現代的な生活課題として認識することを出発点とした実践、持続可能な社会の一員として豊かでよりよい生活をめざしていく気持ちを高めることに取り組んだ実践などが報告された。これらの実践をもとに、具体的な討論を行うことができた。
保健体育(体育)
「体育でどのような子どもを育てるか、自ら考え行動する子どもをどう育てるか」を大テーマに、次の点を研究主題として、発表・討論が行われた。
⑴ かかわり合いを大切にした授業づくり
⑵ 学年に応じた体力向上と技能習得
どのリポートにも、指導方法の工夫や仲間とのかかわり方に関するさまざまな工夫のある実践が報告された。討論では、技能習得のための指導法などについて、活発な意見が出された。
保健体育(保健)
「子どもが生活の主体となるための健康教育」をテーマに、さまざまな健康課題に対応した指導方法や教材・教具を工夫した実践、保健学習や総合学習の取り組み、体験活動を重視した実践などが報告された。報告を通して、健康に対する意識の高まりや健康課題の解決にむけての実践力が着実に高まってきている様子が感じられた。
自治的諸活動と生活指導(小学校)
「たくましく生きる子どもを育てよう」をテーマとして、活発な討論がなされた。
子どもたちのよりよい人間関係を築くために、学級や学年、異学年交流を通して活動する実践が数多く報告された。また、子どもたちが自分自身を見つめ、自ら課題を見つけて取り組むことで、達成感や成就感を味わい、豊かな人間性を身につけていく実践も報告された。その他にも、全校体制で子どもたちの基礎的な学習規律や生活習慣を高め、学級活動や行事、係活動などを通して子どもたちの成長をめざす実践も報告された。
これらの実践報告をもとに、子どもたちの活動のあり方や意義、子どもたちの実態のとらえ方やそれをふまえた教員の支援のあり方について熱心な討論が展開された。
自治的諸活動と生活指導(中学校)
「たくましく生きる子どもを育てよう」をテーマに、活発な討論がなされた。
人権について考える実践や外国籍の子どもの育成に関する実践、学級活動や学校行事を生かしながら、個と集団の力を高める活動や生徒会活動、家庭・地域との連携を通じて子どもの成長をめざす実践が報告された。
これらの実践報告をもとに子どもたちの実態をふまえた支援のあり方について議論が深められた。
能力・発達・学習と評価
家庭や地域と連携し、命について考えることで、子どもの自己有用感を深める実践や地域の特色である景観について学習することで、郷土への誇りや愛着を深める実践、少人数指導やグループ活動など、一人ひとりの学びを大切にした学習指導の実践などが報告された。
自らの考えを表現する力を高めるための取り組みでは、ICT機器を効果的に活用し、表現したいという意欲を高める実践や、子どもがクリアファイルやホワイトボードシートを活用する実践が報告された。
特別支援教育
「豊かに生きるための力を育む」というテーマのもとに61本のリポートが報告された。
子どもの教育的ニーズを的確に把握し、学習意欲を高めるような教材・教具を工夫した実践、子どもの現在や将来の生活に直接結びつく力を身につけさせるための実践、人とかかわる力やコミュニケーション能力を高めるための実践などが報告された。
進路指導
小学校では、コミュニケーション能力の育成や自己肯定感の高揚をめざした実践が報告された。行事や学級活動の中で、これらの力を高めていくことの必要性が確認された。
中学校では、職場体験学習を軸として、事前・事後の指導を系統的に行っていく実践が多数報告された。働くことの意義などについて事前に考えさせることで、職場体験学習がより有意義なものになることが確認された。
教育条件整備
「子どもの学習権の保障のために」を主題に、ICT教育にかかわる条件整備、さまざまな教科指導にかかわる条件整備について報告された。
ICT機器の利用状況や問題点をアンケートによる調査でまとめた実践や、ICT機器を授業の中で効果的に取り入れ、子どもたちの学びを深めた実践が報告された。また、中学校で必修となった武道の実態や課題をアンケートによる調査でまとめた実践、保健指導における実践を通して環境面で整えるべき条件整備についての報告も提案され、熱心な討論が行われた。
過密・過疎、へき地の教育
生活科を通して、友だちや地域とのかかわりを深める実践、へき地における地域素材や人材を積極的に活用した実践、離島における少人数指導と、小中連携推進事業を取り入れた学習指導の実践など、4本が報告された。
地域の自然や伝統文化を生かした職場体験学習を通して、地域の特色やよさを見つめ直させるとともに、地域とのかかわり合いを深めることで、地域に生きる人の思いに迫らせた実践、少人数指導だからこそできる指導を工夫したり、島の特色を生かした小中連携教育を推進したりすることで、基礎・基本を定着させた実践などが報告された。いずれのリポートも、へき地校の抱える問題点を考慮しながらも、小規模校の利点を生かし、地域素材や人材を活用した実践の報告がなされた。
環境問題と教育
自分にできる栽培活動を通して環境問題と向き合っていく実践、学校だけでなく家庭や地域、外部講師などとのつながりを大切にしながら環境問題解決にむけ、学びを深めていく実践など、各学校の特色や実態をふまえながら取り組まれた実践が、小学校から1本、中学校から6本報告された。
子どもたちの環境に対する意識を高め、よりよい環境づくりに目を向けさせ、確かな実践力や行動力の育成をめざした実践に力を入れている様子が感じられた。
情報化社会の教育
教科などの授業でICT機器や教育用コンテンツを有効に活用することにより、学習意欲や学習理解の向上をはかりながら学習のねらいに迫っていく実践が報告された。
また、取り上げる題材や発表の場・対象を工夫することにより、必要な情報を主体的に収集・整理し、相手を意識した情報発信をするといった情報活用能力を育成する実践も報告された。
さらに、実際に起きているインターネット上の問題点に着目し、子どもの実態にあわせて情報モラルの意識や態度を育てる実践も報告された。
子どもを中心にすえたICT実践を学び考えることができた実り多い議論になった。
読書・学校図書館
学校間・地域間で差はあるものの、図書館の環境整備や公共図書館との連携をすすめながら、読書に親しませる実践が行われている。
しかし、学級担任兼司書教諭という立場で、多忙のなか、図書館の管理運営や読書指導を広めていくことの難しさがあることが討論を通してわかった。
読書に継続的に取り組めるように、読書活動、図書館の管理運営に関する実践、発達段階に応じた図書資料を活用した調べ学習などの「生きる力」を育む実践などが数多く報告された。
総合学習
地域の特色を生かして教育課程を自主編成し、子どもたちに「生きる力」と地域への愛着や誇りを育んだ実践が数多く報告された。また、子どもたちに身につけさせたい力を明らかにして、人とのかかわりや教科との関連を生かしながら、めざす子どもの姿に迫った実践も多く、子どもたちの変容の様子が報告された。さらに、ESDやキャリア教育、福祉、食育といった今日的課題を取り上げ、子どもたちが主体的に課題に取り組めるように工夫された実践が報告された。時間数が削減された中でも、各学校で確かな実践がすすめられていることが感じられた。
カテゴリー:更新情報, 教育研究愛知県集会 →2022年以降の記事は愛教組連合ホームページへ, 子どもを中心にすえた教育研究を